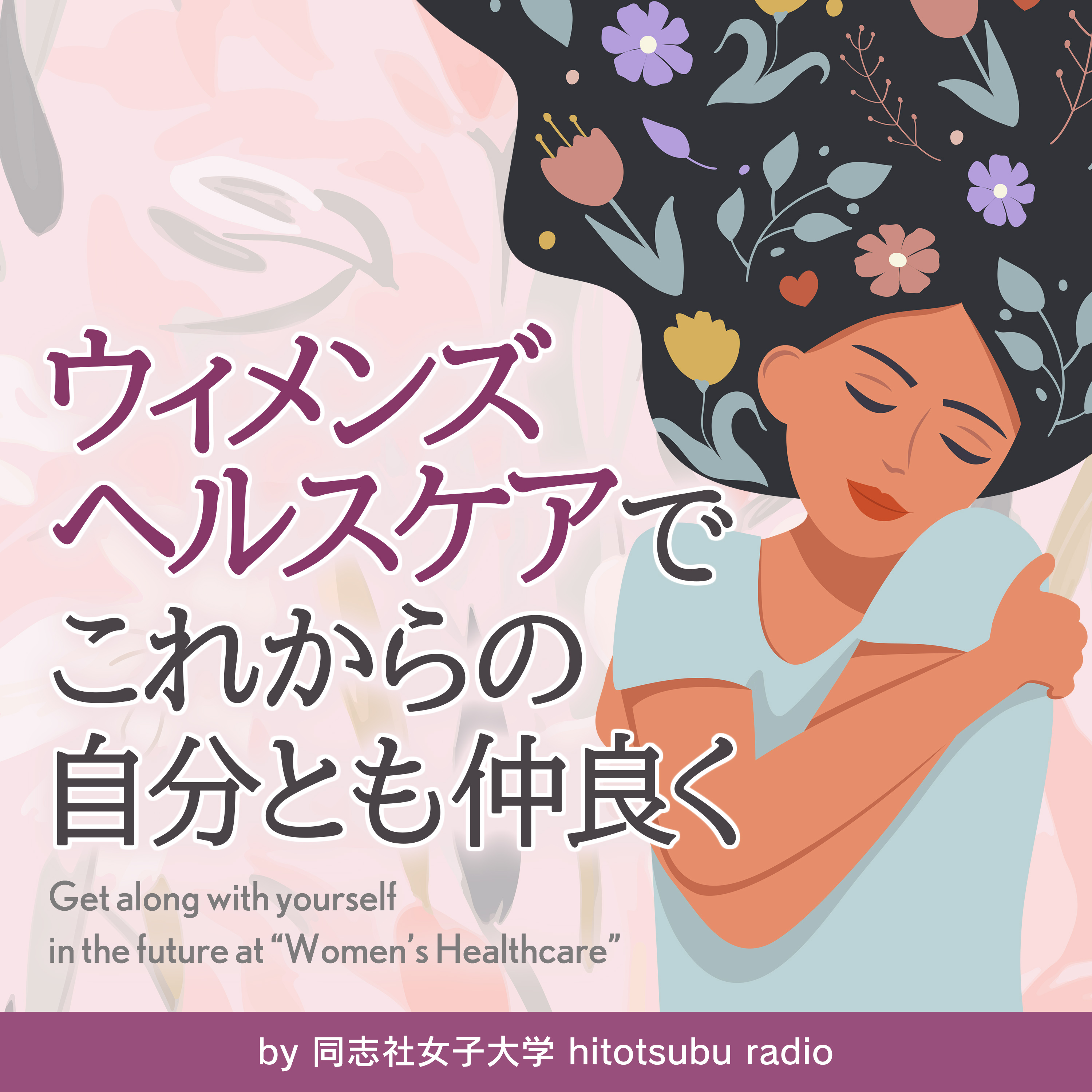新たな気づきが生まれる場に。
女性の生涯の健康を支える助産師があなたの街にもいます
「助産師=出産の専門家」というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。
実は助産師は、妊娠・分娩期にとどまらず、思春期から更年期まで、女性のライフステージ全体を支える医療職です。
地域や企業と連携しながら、孤育てや産後うつといった社会課題の解決にも取り組んでいます。

社会の変化に伴い広がる助産師の役割
「助産師と看護師はどう違うの?」
よくある質問です。助産師は、2025年7月現在、女性だけが取得できる国家資格で、看護師の国家資格が必須となります。医師の指示がなくても正常分娩の介助ができ、開業権を持っている点が特徴です。そのため病院勤務だけでなく、フリーランスや助産所(助産院)の運営といったキャリアの選択肢があります。
病気やケガを患っている患者さんがケア対象となる看護師に対して、助産師は妊産婦や新生児がケア対象の中心です。もちろん看護師資格も持っているので、患者さんのケアもできます。対象者に寄り添い、「一人ひとりの強みを伸ばす」ことに着目してケアの方法を考えます。そして共にゴールを見つけていきます。人をエンパワメントすることに長けており、助産師として臨床経験のある私自身を含めてエネルギッシュな女性が多いと感じます。
少子高齢化・核家族化をはじめ、昨今の社会変化に伴って、助産師に期待される分野が広がってきました。なかでも女性一人での不安な「“孤育て”(孤独に子育てをすること)」の問題が浮き彫りになる一方で、妊娠・出産を経て仕事を続ける女性も増えています。そうした女性を支える役割を、助産師が担っています。
例えば東京都品川区では、専属の助産師が妊娠から産後3ヶ月まで区内在住者一人ひとりをウェラブル端末とオンライン面談で支援する「オンラインMy助産師事業」を2025年度にスタートしました。先着順ですが利用は無料で、妊婦のパートナーも支援対象です。
育休中の支援とキャリア形成への効果
品川区のような取り組みが始まったとはいえ、国が進める女性活躍推進に対して、就業と育児の両立支援は決して十分ではありません。育児休業中の女性の多くは、育児や復職後の両立に不安を感じていると考えられています。
そうしたなか私たちは、企業との共同研究を行いました。この研究は、女性が抱える健康課題をテクノロジーで解決するフェムテック(女性の健康課題に特化したテクノロジー)事業の一環として、育児休業中の女性を対象に通所型産後ケアとオンラインカウンセリング(専門職との対話をインターネット経由で行う心理・健康相談)を実施し、産後女性の健康やキャリア形成における意識の変化を明らかにするものです。
産後ケアとは、助産師を中心とした専門スタッフが産後の母親の心身のケア、乳児の沐浴やケア、育児に関する相談・指導を行うもので、通所型、訪問型、滞在型があります。今回は、産後2年以内の育児休業中の母親と幼児が施設に通う通所型で研究を行いました。 結果、産後ケアやオンラインカウンセリング(OC)の利用は、自身と同僚女性の健康リテラシーの向上や今後のキャリア形成を考える機会になり、復職後の不安が軽減されたというデータが出ました。健康経営の一環として、多くの企業に産後ケアやオンラインカウンセリング(OC)を導入してもらいたいです。
助産師による産後ケアで社会課題の解決へ

妊産婦のメンタルヘルスへの支援が社会課題となるなか、私たちは通所型産後ケア利用前後の女性の心身の変化を明らかにする研究も行いました。産後うつ病を見分けるツール「エジンバラ産後うつ病質問票」を活用した調査の結果、産後うつの可能性がある女性の割合は減少し、助産師による産後ケアが課題解決に役立つことが明らかになりました。
少子化・核家族化が進み、子どもと接した経験がなく、相談相手もないなかで不安を抱えて女性1人が慣れない育児を担う「孤育て」が、妊産婦の自殺や産後うつの要因になっています。ハイリスクの家庭は病院や行政の連携による見守りが行われていますが、外からは見えない苦しさを抱えている女性もいます。
産後ケアは地域の助産所でも行われており、母親が集まる場所を提供している助産師もいます。公費補助もありますので、ぜひ活用してください。
思春期から更年期までヘルスケアの相談に対応
そのほかの主な助産師の活動を紹介します。
1.プレコンセプションケア推進
男女を問わず性や妊娠への正しい知識を身につけ、健康管理を促す「プレコンセプションケア」がヘルスケアの1分野として注目されています。若いうちから将来のライフデザインを考えて健康管理に向き合うための知識やアドバイスの提供を助産師が担っています。 日本では長くタブー視されてきた性教育についても、助産師が担う場面が増えてきました。例えば出前授業思春期教育として、幼稚園児・保育園児から高校生や保護者を対象に、生と性を知り命の大切さを伝える「いのちの教育」を行っています。
2.思春期の月経や更年期の悩み相談
助産師は全員女性なので、思春期の月経の悩みなど女子児童・女子生徒が相談しやすいこと、生活習慣の見直しからアドバイスするため、ヘルスケアの基礎知識を得られる点が特徴です。更年期以降のヘルスケアの悩みにも対応しています。
3.不妊の悩み相談
不妊についても助産師に相談できます。治療ではなく、まずは食事や運動をはじめとした生活習慣の見直しから、地域の助産所などでアドバイスをしています。相談にはそれぞれ利用料がかかるため、事前に助産師に確認してください。
地域の助産師をぜひ頼ってください
助産所での出産数は全出産数の1%程度で、お産を扱う施設は減っています。しかし病院とは違い、多くの施設は家族で訪ねることができ、出産の立ち会いもできます。妊娠中から家族ぐるみで助産師が関わるため、妊産婦が安心できるメリットもあります。 インターネットなどで地域の助産師を見つけて、マタニティケアとウイメンズヘルスケアを併せもった健康支援の心強い“かかりつけ助産師”として頼ってください。
ひとつぶラジオ
同志社女子大学の教員を迎えて、日々を豊かにするヒントをお届けする「ひとつぶラジオ」。
こちらでは、和泉教授による「「ウィメンズヘルスケア」でこれからの自分とも仲良く」を公開中です。
ぜひ、合わせてご覧ください。
取材に関するお問い合わせ
取材のお申込みをいただく際には、以下の注意事項をご確認いただき、「取材申込書」をご提出ください。